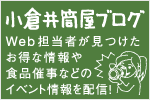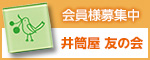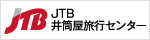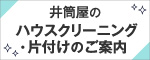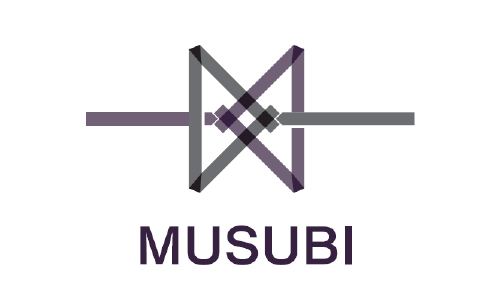
私は新館7階『MUSUBI』に勤務しております終活アドバイザーの宮本と申します。
『終活』に関して「何をしておくべきなのか」、アドバイスや提案を定期的に発信してまいります。ご参考いただければ幸いです。
今回は、「介護」についての話です。内容が複雑でわかりにくいため、3回に分けて説明いたします。

1.公的介護制度のしくみ
公的介護保険制度で利用できるサービスのことを「介護サービス」といいます。誰が、どのような状態のときに、どのような介護サービスを利用できるのか説明してまいります。
1)介護保険の対象となる人
40歳以上の人は介護サービスを受けることができますが、年齢により第1号被保険者:65歳以上の人、第2号被保険者:40歳以上65歳未満の人に分けられ、それぞれ保険料の決定方法やサービスを利用できる条件が異なります。
2)介護サービスの利用料と自己負担
公的介護保険を利用して介護サービスを受ける場合、1ヵ月あたり一定の限度額までは、利用料の一部負担だけでサービスを受けることができますが、限度額は「要介護度」によって決定します。
①要介護度とは、その人にどの程度の介護が必要か決める基準。公的介護保険の申請をすると、要介護状態が審査されます。
②要支援・要介護の目安
要支援1:身の回りのことはできるが、生活上何らかの支援が必要
要支援2:日常生活の能力が低下し、身の回りのことに一定の支援が必要
要介護1:立上りや歩行が不安定。身の回りの世話に一定の介助が必要
要介護2:立上りや歩行が自分では難しく、身の回りのことに介助が必要
要介護3:立上りや歩行が難しく、身の回りのことや排せつに介助が必要
要介護4:寝たきりに近い生活で、身の回りのことに全面的な介助が必要
要介護5:寝たきり生活で、食事含めて日常生活すべてに介助が必要
※あくまでも目安です。
③利用できる介護サービスの限度額と自己負担割合
公的介護保険では、要介護度に応じて1ヵ月に利用できる介護サービスの限度額が決められており、この金額の範囲内で利用するサービスについては、利用者は利用料の1~3割の負担となります。
※所得が一定以上の人は、自己負担割合が2割または3割。負担割合は要介護認定者に交付される「介護保険負担割合証」で確認することができます。(将来変わる可能性あり)
■1ヵ月あたりの介護サービス限度額
要介護度 | 限度額(円) | 要介護度 | 限度額(円) |
要支援1 | 50,320 | 要介護3 | 270,480 |
要支援2 | 105,310 | 要介護4 | 309,380 |
要介護1 | 167,650 | 要介護5 | 362,170 |
要介護2 | 197,050 |
※但し、限度額を超えてサービスを利用した場合、限度額を超えた部分の利用料は利用者の全額負担となります。
次回は公的介護サービスを利用するために必要な手続きの流れについてご説明いたします。
新館7階「MUSUBI(結び)」では、毎週、各種無料相談会を開催しています。ホームページや井筒屋アプリでも相談会スケジュールを発信していますので、空き情報等をお気軽にお尋ねください。
MUSUBI(結び) ホームページはこちら
担当 宮本・吉本・野田
お問い合わせ
■小倉店新館7階 MUSUBI(メモリアル相談)
TEL:093-522-3620
カテゴリー:イベント・キャンペーン
フロア:新館7階